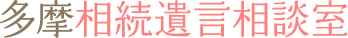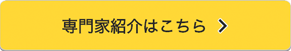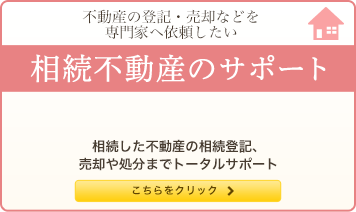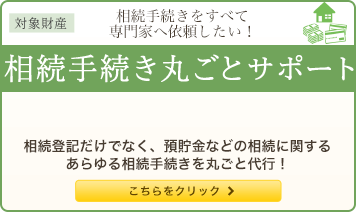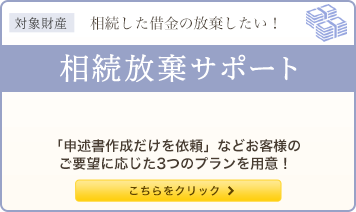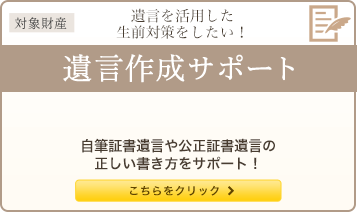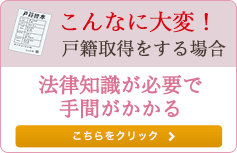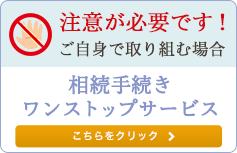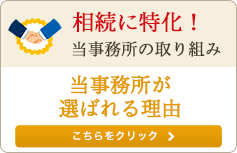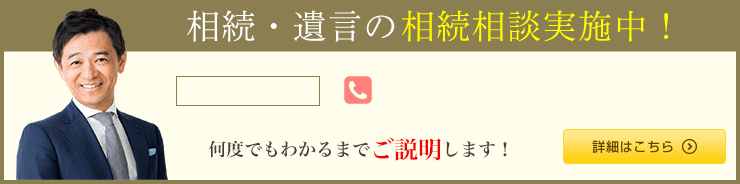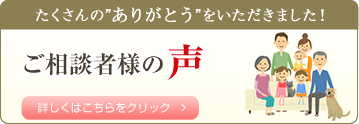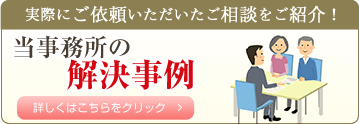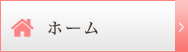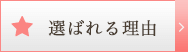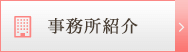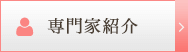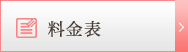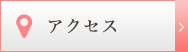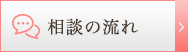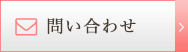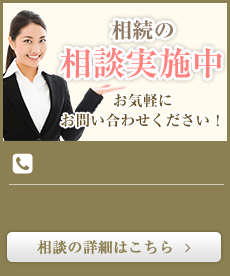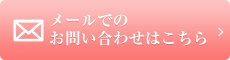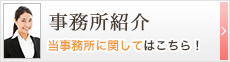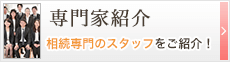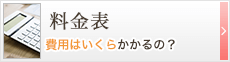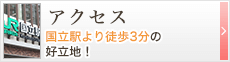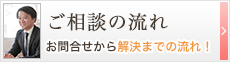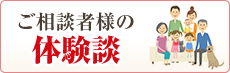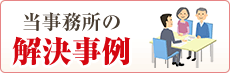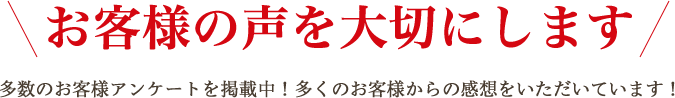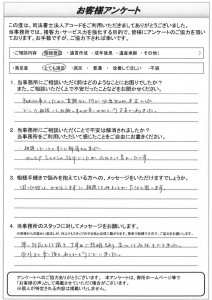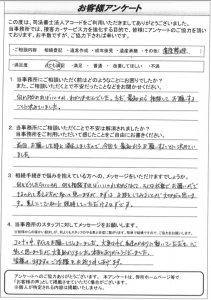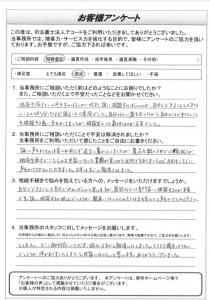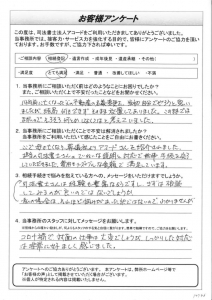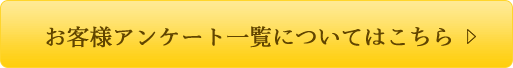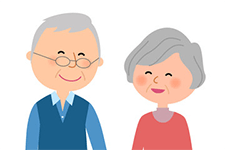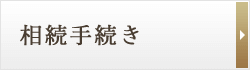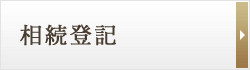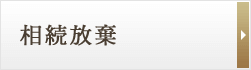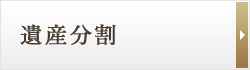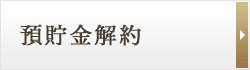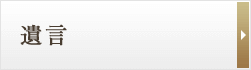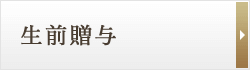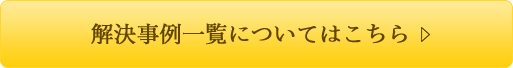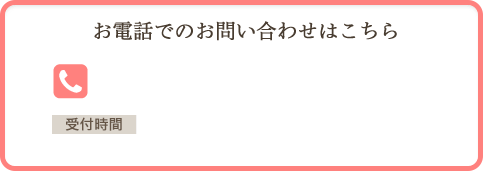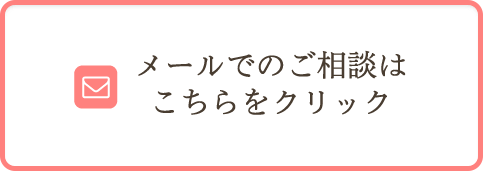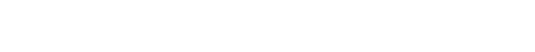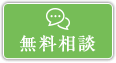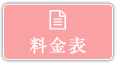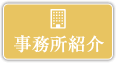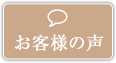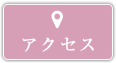売れない土地を相続したらどうする?損する前に知っておきたい対処法6選
相続した実家の土地が売却できず、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。売却ができない土地は、特に維持費や固定資産税の支払いが重荷になります。
また、2024年から施行された相続登記の義務化により、不動産相続時の責任がより明確になりました。これにより、必要としない土地を相続した人々の間で、その対処に困っているという方の声が増えています。
このような状況を踏まえ、ここでは不要な土地を相続してしまった際の効果的な対応策をご紹介いたします。土地の有効活用や売却以外にも、様々な選択肢があることを知っておきましょう。
売却できない土地によくある特徴は?
相続で土地を引き継ぐ際は、その不動産の価値を見極めることが非常に大切です。価値ある土地であれば、譲渡先を見つけやすく、売却の可能性も高まります。
しかし、不動産取引に詳しくない方にとって、土地の価値判断は容易ではありません。特に注意が必要なのは、以下のような特徴を持つ土地です。
・数年以上にわたって使用されていない土地
・別荘地などで利用頻度が極めて低い物件
・隣接地との境界線が不明確な土地
・相続まで存在すら知られていなかった不動産
などが挙げられます。このような特徴を持つ土地は、収益性が低かったり、維持費が高額になる可能性があります。自身が相続する土地がこれらの特徴に当てはまる場合、できるだけ早い段階で対応策を検討することをお勧めします。
土地の放置は許されない!?相続登記義務化で変わったこと
2024年から施行された相続登記の義務化の変更点について解説します。従来も相続登記は推奨されていましたが、新制度下では相続から3年以内に登記を行わない場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。
この制度改正の主な要因は、適切な相続登記が行われないことによって生じる「所有者不明土地」の問題です。相続登記がされないことで、所有者がわからない土地が多発したことを受け、政府は土地管理に関する規制を強化する方針を示しています。
この新制度は単に罰則を設けるだけでなく、土地の適切な管理と利用を促進することを目的としています。この制度変更を契機に、相続した土地の管理や活用について、より積極的に考える必要が出てきたと言えるでしょう。
不要な土地の所有で考えられる危険とは
不動産の相続において、収益性のない土地は様々な課題をもたらす可能性があります。処分に際して予想外の費用が発生したり、相続手続きが滞り、結果として土地が放置されるケースも少なくありません。しかし、こうした土地を放置することは、金銭面以外にも多岐にわたるリスクを生み出す可能性があります。
家族、親族間での争いとなるリスク
相続財産に不要な土地が含まれると、家族や親族間での争いの火種となることがあります。収益価値がない土地は、誰も引き受けたがらないため、相続人同士で押し付け合いになる可能性があります。
また、不動産は世代を超えて引き継がれる可能性があり、そうなった場合は権利関係がより複雑化して、将来の対応を困難にする恐れがあります。
金銭面のリスク
まず、所有者には固定資産税の支払いや土地の維持管理といった継続的な負担が生じます。さらに、適切な管理を怠ると、周辺環境に悪影響を及ぼし、損害賠償請求のリスクが高まる可能性があります。例えば、手入れをされていない樹木が隣地に侵入したり、老朽化した建物が倒壊して被害を与えるといったケースが考えられます。
周辺住民との争いを生むリスク
放置された土地は、周辺住民や土地に対して、様々な問題を引き起こす可能性があります。境界線が不明確になり、近隣住民との間で争いが生じやすくなります。また、草刈り等を適切に行わないと、雑草が自然発火するリスクや不審火にあう可能性もあります。
また、放置された土地は不法行為の温床となりやすい傾向があります。誰も管理していない土地とみなされて不法投棄の標的になったり、犯罪者の隠れ家として悪用されるケースも報告されています。このような状況は、地域の安全を脅かし、治安の悪化につながる可能性があります。
土地の処分で損をしないために!知っておきたい対処方法6選
不要な土地の所有は、多くの方にとって大きな負担となっています。売却しようとしても買い手が見つからず、その間も固定資産税や維持費の支払い、管理の手間に悩まされる方は少なくありません。
さらに、不動産取引の経験が乏しい方にとっては、最適な処分方法を見極めることも一苦労です。専門的な知識が必要な場面も多く、判断に迷うケースが多々あります。このような状況を踏まえ、ここでは売却が困難な土地や、必要としない土地を所有することになった場合に損をしないために、効果的な対応策をご紹介します。
相続放棄
相続財産の中に負担となる土地が含まれている場合、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄を行うことで、不要な土地の所有に伴う責任や税金の負担から逃れることができます。ただし、注意すべき点があります。相続放棄は部分的に行うことはできず、相続財産全てを放棄することになります。
そのため相続財産全体を見て、不要な土地の負担や債務が資産価値を上回る場合、相続放棄を考えるようにしましょう。
相続放棄について動画で解説!
隣地の住民へ譲渡
土地の処分方法として、あまり知られていませんが、隣接する住民への譲渡という選択肢があります。この方法には双方にメリットがあります。譲渡する側は、固定資産税や維持管理の負担から解放されます。一方、受け取る側は、自身の所有地と合わせることで、敷地面積を広げ、土地の価値を高められる可能性があります。
もし近隣住民との交流がない場合でも、法務局で登記簿謄本を入手することで、隣接地所有者の連絡先を知ることができます。これを活用して、譲渡の提案を手紙で行うことも可能です。
相続土地国庫帰属制度
相続で受け継いだ土地は不要だが、相続放棄はしたくないという場合に使えるのが、「相続土地国庫帰属制度」です。この制度を利用すると、特定の条件を満たす土地を国に費用を支払い、引き取ってもらうことが可能になります。
ただし、この制度にはいくつかの留意点があります。まず、全ての土地が対象となるわけではなく、一定の基準を満たす必要があります。また、手続きには審査手数料が必要で、さらに申請が承認された場合は追加の負担金が発生します。利用を検討したい場合は、まずは近隣の法務局に相談してみるといいでしょう。
自治体へ寄付
不要な土地を処分したい場合、居住地の自治体に問い合わせてみることをおすすめします。自治体によっては、土地の寄付を受け付けています。ただし、全ての自治体が寄付を受け入れているわけではないので注意が必要です。
また、寄付した土地は自治体の管理下に置かれ、公共の用途に使用されることになります。そのため、公園や公共施設など、地域社会に役立つ場所として活用しやすい土地でないと、自治体側が寄付を断る可能性もあります。 まずは最寄りの役所等に連絡を取り、土地寄付の可否や条件について確認してみるのがよいでしょう。
専門の引き取り業者を活用する
一般的な不動産取引では売却が困難な土地でも、不動産の引き取りを専門とする業者に相談すれば、処分できる可能性があります。これらの業者は、通常の不動産市場では扱いにくい条件の悪い土地であっても、引き取ってくれることが多いのです。寄付や相続土地国庫帰属制度では対象外となるような土地でも、引き取り業者なら処分できるかもしれません。
土地の所有が大きな負担になっている方は、ぜひ引き取り業者への依頼を検討してみてください。ただし、サービス利用には料金がかかる場合があるので注意が必要です。
また、残念ながら不動産引き取り業界には、悪質な業者も存在します。彼らは詐欺的な取引を行ったり、土地処分に悩む所有者の弱みにつけ込んだりすることがあるのです。そのため、依頼先の業者の信頼性を十分に確認してから契約を結ぶことが大切です。過去の実績や顧客の評判などを調べ、信用できる業者を選ぶようにしましょう。
マッチングサービスを利用する
近年、注目されているのが土地のマッチングサービスです。このサービスを利用して不要な土地を登録することで、地域の不動産屋では探すことができなかった全国の土地購入希望者に向けて情報を発信できます。
マッチングサービスでは、個人間での取引が行われるため、仲介手数料がかからないというメリットもあります。また、自分の希望する価格で土地を売却できる点も魅力の一つです。
ただし、サービス利用にあたって手数料が必要な場合もあるので、事前に確認しておくことが大切です。 日頃からインターネットを使った取引に慣れている方は、土地のマッチングサービスを活用してみるのもよいでしょう。
いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら
まとめ
不要な土地の処分は、相続人にとって頭の痛い問題となることがあります。特に不動産取引に関する知識や経験が乏しいと、どのように土地を手放せばよいのか分からず、途方に暮れてしまうかもしれません。
そのような状況に直面した際は、専門家に相談するのも一つの選択肢です。相続に精通した士業の方々は、豊富なノウハウと経験を持っているため、円滑に土地の処分を進めることができるでしょう。 専門家に依頼することで、法的な手続きや税務上の問題など、相続にまつわる複雑な手続きをスムーズに処理できます。特に相続が絡むと当事者同士で解決が難しい場合もあるので、まずは一度相談してみることをおすすめします。
この記事を担当した代表司法書士

アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
-
司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
-
遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
-
司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。