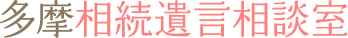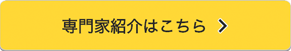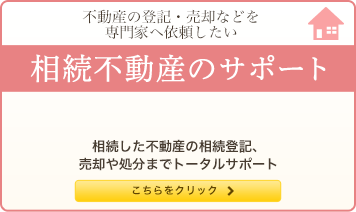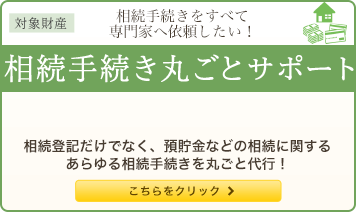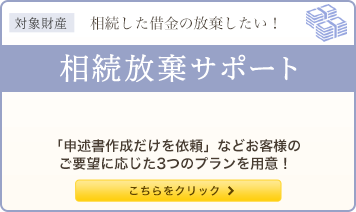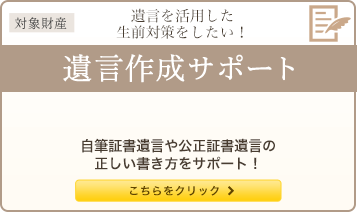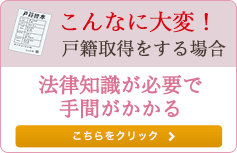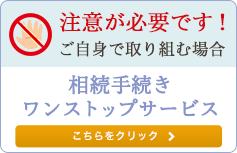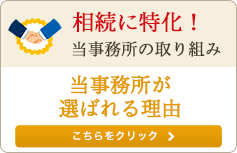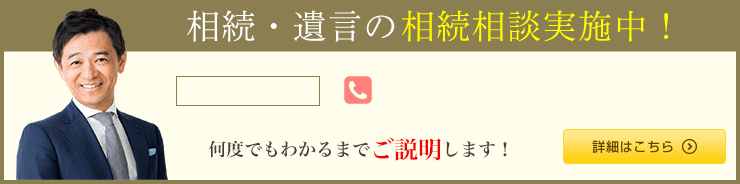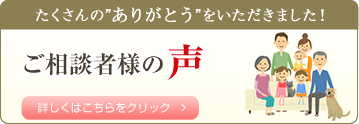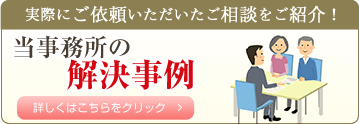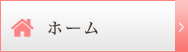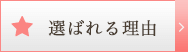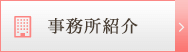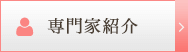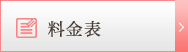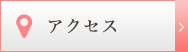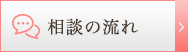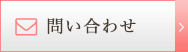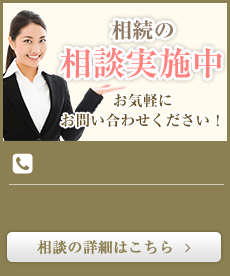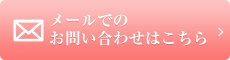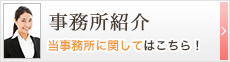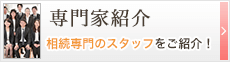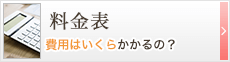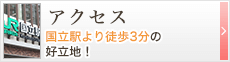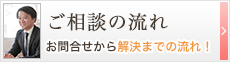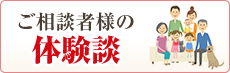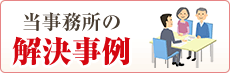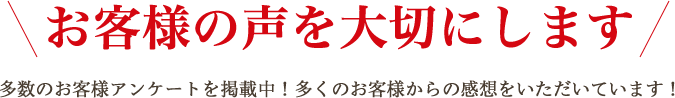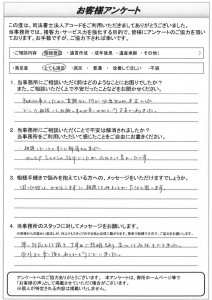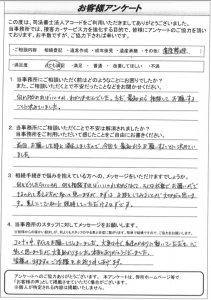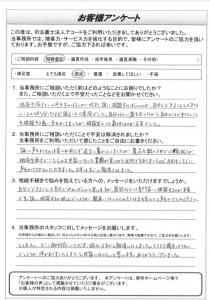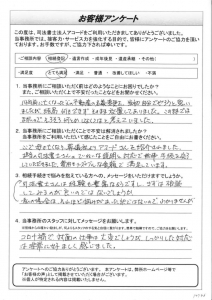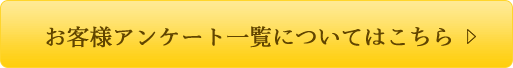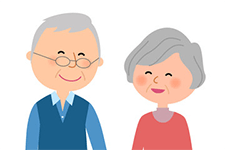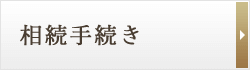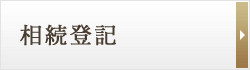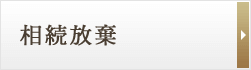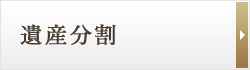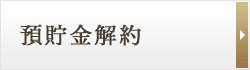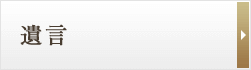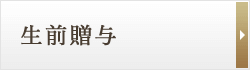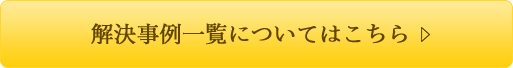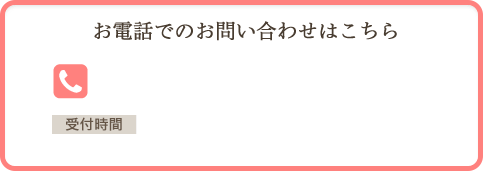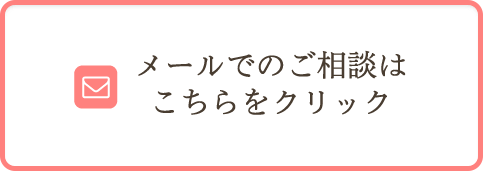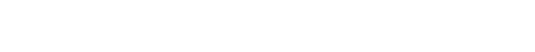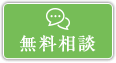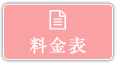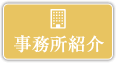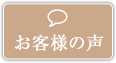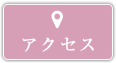離婚から10年…元夫と共有のままだった自宅不動産。住宅ローンを残した状態で単独名義に変更した方法とは?

「離婚をしたけれど、家の名義変更をしないまま何年も経ってしまった」
「住宅ローンが残っているので、名義変更は無理だと諦めていた」
実は、このようなご相談は司法書士法人アコードに寄せられる案件の中でも、非常に多いケースの一つです。 離婚に伴う財産分与は、本来であれば離婚成立と同時に、あるいは離婚後速やかに行うのが理想です。しかし、日々の生活の忙しさや、相手方との話し合いの煩わしさ、そして「住宅ローン」という大きな壁に阻まれ、手続きが先送りされてしまうことが少なくありません。
今回は、離婚から10年が経過してからご相談をいただき、住宅ローンが残る不動産を元ご主人との「共有名義」から、ご依頼者様の「単独名義」へと無事に変更できた解決事例をご紹介します。
なぜ10年も放置すると危険なのか? ローンがある家はどう扱えばいいのか? 実際の事例をもとに、司法書士が徹底的に解説します。
1. ご相談者様の状況と抱えていた悩み
解決事例の概要
-
ご依頼者様: 40代女性(元妻)
-
相手方: 40代男性(元夫)
-
離婚時期: 約10年前
-
対象不動産: 立川市内の一戸建て(元夫とご依頼者様の共有名義)
-
住宅ローン: あり(連帯債務)
-
居住状況: 離婚後、元夫が退去し、ご依頼者様とお子様が継続して居住中
ご相談の背景
ご夫婦は10年ほど前に協議離婚をされました。当時は若くしての離婚だったこともあり、財産分与に関する取り決めや、公正証書などの書面作成は一切行っていませんでした。 唯一の大きな財産であるご自宅は、結婚当初にペアローン(連帯債務)で購入したもので、名義もローンも夫婦二人の名前が入ったままでした。
離婚後、元夫は家を出て行き、ご依頼者様がお子様と住み続けることになりました。それに伴い、住宅ローンの返済も事実上、ご依頼者様がお一人で負担されてきました。
「いつかは名義を変えなくては」 そう思いながらも、日々の忙しさに追われ、また元夫と連絡を取る心理的なハードルもあり、気づけば10年という月日が流れていました。 しかし、お子様の進学やご自身の将来を考えたとき、「このまま元夫と共有の状態にしておくのは怖い」と一念発起され、当事務所へご相談に見えられました。
2. この事例の「3つのハードル」
この案件には、解決しなければならない法的・金融的なハードルが大きく3つありました。
① 住宅ローンが「連帯債務」であること
ご自宅のローンは、夫婦が互いに連帯して全額の返済義務を負う「連帯債務」の形をとっていました。 通常、不動産の名義を妻の単独にするならば、ローンも妻の単独名義に借り換えるのが筋です。しかし、借り換えには妻単独での厳格な審査があります。今回のご依頼者様は、返済実績は十分でしたが、年収等の条件で単独での借り換え(または夫の債務引受)が現時点では難しい状況でした。
② 金融機関の承諾が必要不可欠
「ローンはそのままで、名義だけ変えればいいのでは?」と思われるかもしれませんが、これは非常に危険です。 住宅ローンの契約約款には、通常**「所有者を変更する場合は、事前に銀行の承諾を得ること」**という条項が入っています。もし無断で名義変更を行うと、契約違反となり、残りのローン全額を一括返済するよう求められるリスクがあります。 したがって、銀行と交渉し、「ローン名義は今のまま(連帯債務)で、所有権だけを移転する」ことの承諾を得る必要がありました。
③ 離婚協議書が存在しない
10年前の離婚時に書面を作成していなかったため、「この不動産を財産分与として譲渡する」という法的な根拠がありませんでした。 登記(名義変更)を行うには、その原因となる公的な合意文書(離婚協議書や財産分与協議書)が必須となります。
3. アコードが提案した解決スキーム
当事務所では、ご依頼者様の「今の家に住み続けたい」「将来の不安をなくしたい」というご希望を最優先に考え、以下のステップで手続きを進めました。
ステップ1:元夫との合意形成と銀行への事前確認
まず、ご依頼者様を通じて元夫と連絡を取り、「住宅ローンの支払いは今後も妻が責任を持って行う代わりに、持分を妻に渡してほしい」という点での合意を取り付けました。 並行して、借入先の金融機関に対し事情を説明。「妻が実質的に返済を継続している実績」と「離婚による財産分与であること」を伝え、所有権移転の承諾を得る交渉を行いました。 結果、今回は例外的に「債務者は連帯債務のまま変更せず、所有権のみ妻単独とする」ことについて、金融機関からの内諾を得ることができました。
ステップ2:離婚協議書(財産分与協議書)の作成
法的効力のあるしっかりとした「離婚協議書」を当事務所で作成しました。 ここには以下の内容を明確に盛り込みました。
-
財産分与の合意: 不動産の元夫持分を、財産分与として妻へ譲渡すること。
-
債務の負担: 住宅ローンの残債務については、妻が責任を持って返済し、元夫には迷惑をかけないこと(内部的な求償権の放棄など)。
-
清算条項: 「本件以外に、両者間に債権債務は存在しない」という文言を入れ、後日の金銭トラブルを防止すること。
ステップ3:所有権移転登記の申請
作成した協議書と、元夫から預かった印鑑証明書等を使用し、法務局へ名義変更の登記申請を行いました。 これにより、登記簿上の所有者は正式に「ご依頼者様お一人」となりました。
4. なぜ「共有のまま」放置してはいけないのか? 将来の重大リスク
今回の事例のご依頼者様が、「今、動こう」と決断されたのは本当に賢明な判断でした。 もし、このまま不動産を元夫との共有名義で放置し続けていたら、将来的に取り返しのつかないトラブルに巻き込まれる可能性が高かったからです。
ここでは、離婚後の共有不動産に潜む3つの重大リスクについて解説します。
リスク① 元夫が再婚し、亡くなった場合(相続トラブル)
もし、名義変更をしないまま元夫が再婚し、その後に亡くなったとします。 そうすると元夫の持分は、ご依頼者様ではなく「元夫の再婚相手」や「その子供」に相続されます。 結果として、ご依頼者様が住む家が、「全く面識のない赤の他人との共有」になってしまうのです。 こうなると、将来家を売りたいと思っても相手の同意が必要になりますし、最悪の場合「持分を買い取ってほしい」と高額な金銭を要求されたり、「共有物分割請求訴訟」を起こされ、家を手放さざるを得なくなることさえあります。
リスク② 元夫が借金をし、家が差し押さえられる(競売リスク)
不動産の持分は、立派な資産です。 もし元夫が事業に失敗したり、消費者金融で多額の借金を作ったりした場合、債権者は元夫の「不動産持分」を差し押さえることができます。 持分が競売にかけられれば、落札した不動産業者や投資家が、新しい共有者として乗り込んできます。 平穏な生活は脅かされ、最終的には家全体が競売にかけられる恐れもあります。
リスク③ 認知症による「資産凍結」
元夫が高齢になり、認知症を発症して判断能力を失ってしまった場合、不動産の手続きは一切できなくなります。 売ることも、貸すことも、名義を変えることもできません。成年後見人をつけるなどの大掛かりな手続きが必要となり、実質的に不動産が「凍結」されてしまいます。
こうしたリスクは、時間が経てば経つほど高まります。 「相手と連絡がつくうちに」「相手が元気なうちに」手続きを済ませておくことが、ご自身とお子様の生活を守る唯一の方法なのです。
5. よくある疑問:税金と時効について
今回のケースで、ご依頼者様が特に心配されていたのが「税金」と「時効」の問題でした。これらについても解説します。
Q. 夫から持分をもらうと「贈与税」がかかるのでは?
A. 原則としてかかりません。 離婚に伴う財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を清算する行為であり、新たに利益を受ける「贈与」とは性質が異なるからです。 ただし、以下の場合は例外的に課税される可能性があります。
-
分与された財産額が、婚姻中の協力度合いに比して「多すぎる」場合(過剰な部分に課税)。
-
離婚が贈与税や相続税を免れるための偽装であったと認められる場合。 今回のケースでは、住宅ローンの残債も多く、実質的な資産価値と分与のバランスが適正であったため、贈与税の対象にはならないことをご説明し、ご安心いただきました。 ※登録免許税(登記をする際にかかる税金)や、不動産取得税は別途考慮する必要があります。
Q. 10年前の離婚ですが「時効」で請求できなくなるのでは?
A. 合意があれば手続き可能です。 民法では、家庭裁判所に財産分与を請求できる権利(除斥期間)は「離婚から2年」と定められています。 しかし、これは「相手が話し合いに応じない場合に、裁判所に決めてもらえる期間」のことです。 2年を過ぎていても、当事者同士が話し合って「財産分与として名義を変えよう」と合意することは自由であり、法律上も有効です。 今回は、元夫の協力が得られたため、10年後であっても「財産分与」を原因とする登記が可能でした。 逆に言えば、相手が拒否をした場合、2年を過ぎていると強制的に名義を変えることはほぼ不可能になります。その意味でも、相手との関係がこれ以上疎遠になる前に行動できたことが、解決の鍵となりました。
6. 専門家へ依頼するメリット
今回の事例のように、離婚後の不動産名義変更には、法律、税金、そして金融機関との交渉という複雑な要素が絡み合います。 ご自身で手続きしようとすると、銀行との交渉で言葉に詰まったり、書類の不備で法務局に何度も通ったりと、大変な労力を要します。また、協議書の文言一つ間違えるだけで、将来のトラブルの種を残してしまうこともあります。
司法書士法人アコードにご依頼いただくことで、以下のメリットをご提供できます。
① ワンストップサービス
離婚協議書の作成から、銀行との折衝、法務局への登記申請まで、全ての手続きを一貫してサポートします。あちこちの窓口へ行く必要はありません。
② 将来を見据えた法的書面の作成
単に名義を変えるだけでなく、「後で借金を請求されないか?」「税金は大丈夫か?」といった周辺のリスクまで考慮し、法的に不備のない協議書を作成します。
③ 心理的負担の軽減
元配偶者とのやり取りは、精神的に大きなストレスとなるものです。登記の専門家が間に入り、事務的な手続きを主導することで、離婚した相手と改めて会って財産の話しをしたりすることなく手続きが完了することで、ご依頼者様の心理的な負担を最小限に抑えます。
まとめ:過去を清算し、安心できる未来へ
今回のご依頼者様は、無事に全ての手続きを終え、名実ともに「自分の家」となったご自宅で、晴れやかな笑顔を見せてくださいました。 「10年間、心のどこかでずっと引っかかっていた重荷が下りました。これで子供たちにも迷惑をかけずに済みます」 そのお言葉が、私たちにとっても何よりの喜びです。
離婚に伴う不動産の問題は、放置すればするほど解決が難しくなります。 「うちはもう何年も前のことだから…」 「ローンが残っているから無理だろう…」 そう諦める前に、まずは一度、専門家の目を通してみませんか?
当事務所では、今回のように複雑な事情を抱えた解決実績が多数ございます。 現在の状況を丁寧にヒアリングし、あなたにとって最適な解決方法をご提案いたします。 まずはお気軽にご相談ください。
この記事を担当した代表司法書士

アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
-
司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
-
遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
-
司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。