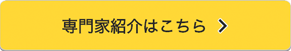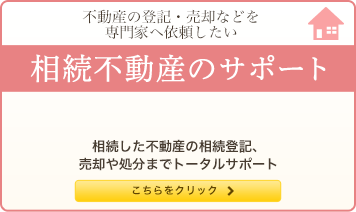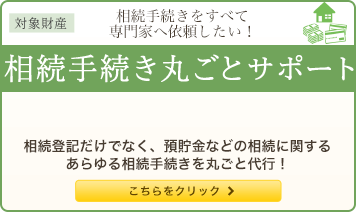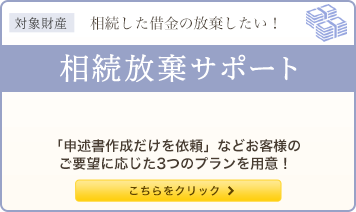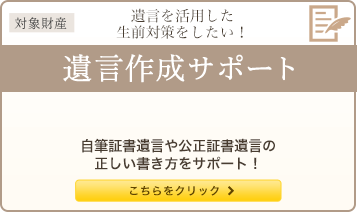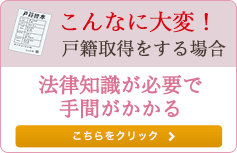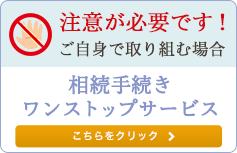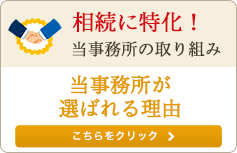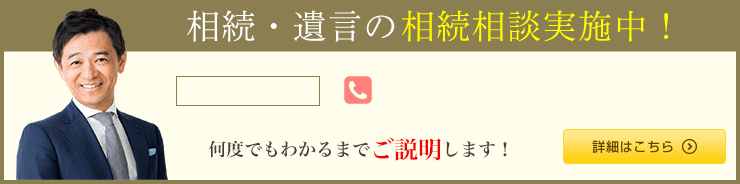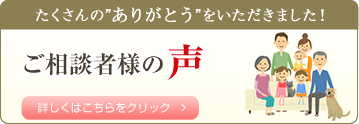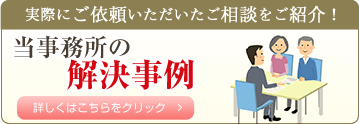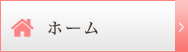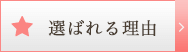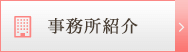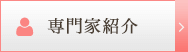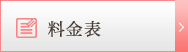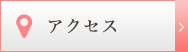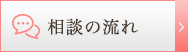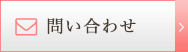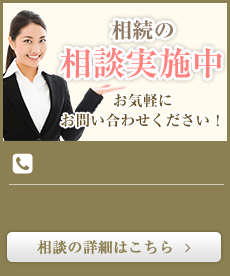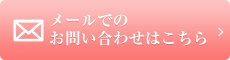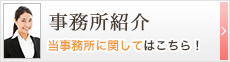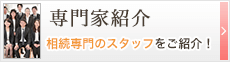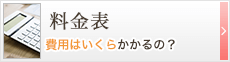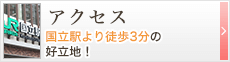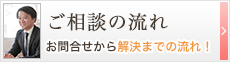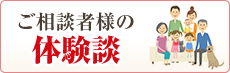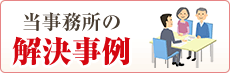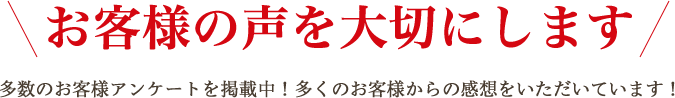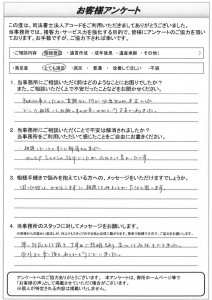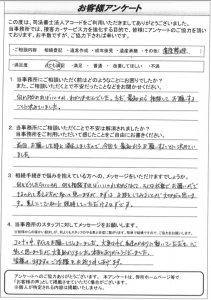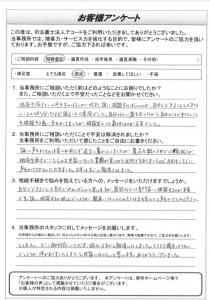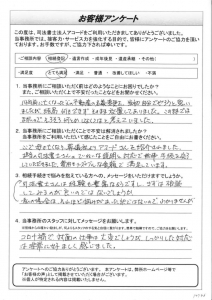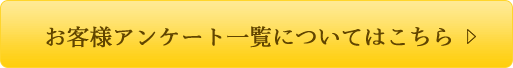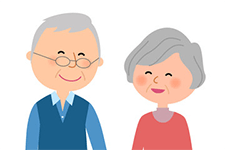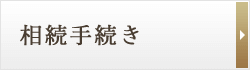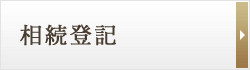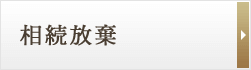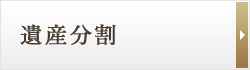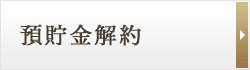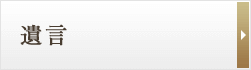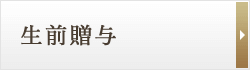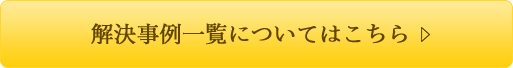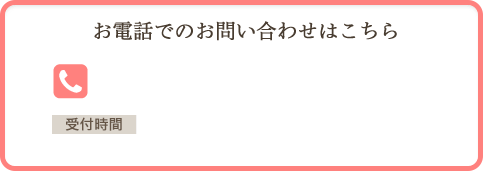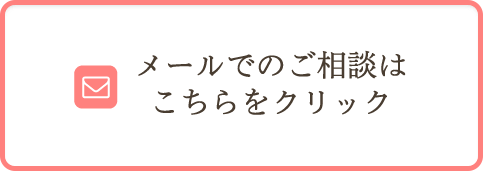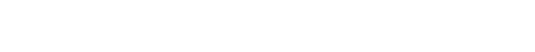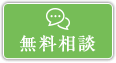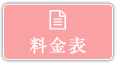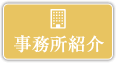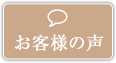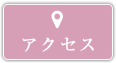相続登記に必要な書類をすべて解説!相続登記には期限があります
「相続登記」とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することです。
つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。
相続登記の手続きには、提出しなければならない書類がいくつかあります。
本記事では、相続登記に必要な書類をすべて解説します。
【一覧表】相続登記の手続きに必要な書類
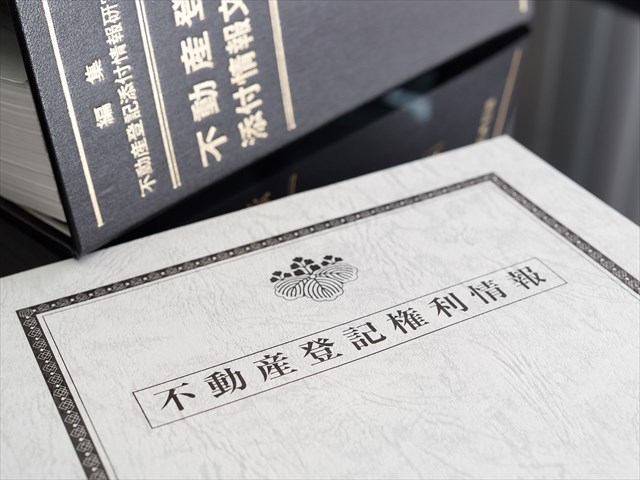
相続登記に必要な書類の一覧です。
基本的には被相続人と相続人の欄の書類だけでよいのですが、ご状況によってはその他の欄の書類も必要になることがあります。
| 被相続人 | ・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 ・住民票の除票(または戸籍の附票) |
| 相続人 | ・戸籍謄本(または戸籍抄本) ・住民票 |
| その他 | ・登記申請書 ・固定資産評価証明書 ・相続関係説明図 ・遺産分割協議書 ・印鑑証明書 ・不在籍証明書、不在住証明書 ・登記済権利証 ・上申書 ・相続放棄申述受理証明書 ・在留証明書 ・署名証明書 |
相続登記に必要な各書類について

相続登記に必要な各書類について詳細を解説します。
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
被相続人の書類として、「戸籍謄本、除籍津尾本、改製原戸籍」が必要となります。
戸籍謄本、除籍津尾本、改製原戸籍は出生~死亡までのすべての履歴が証明できるものでなくてはなりません。
つまり、生まれたときに作成された筆頭者が親や祖父母の戸籍謄本から、筆頭者が変更され作成されたもの、法改正で再作成されたもの、入籍や転籍時新たに作成されたもの、出生~死亡までの履歴があるものをご用意いただく必要があります。
各1通ずつではなく、出生から死亡まで繋げた戸籍謄本等が必要なことにも注意してください。
なお、法定相続情報一覧図を提出する場合は戸籍謄本等の提出は不要になります。
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
被相続人の書類として、「住民票の除票」または「戸籍の附票」が必要です。
登記簿に記載されている人物と戸籍上で亡くなった方が同一人物であることを証明するためです。
登記簿上の住所及び本籍地の記載のある、住民票か戸籍の附票を用意してください。
本籍地と登記簿上の住所が同じ場合は、住民票等がなくても手続き可能です。
相続人の戸籍謄本(または戸籍抄本)
相続人の書類として、「戸籍謄本」または「戸籍抄本」が必要です。
不動産を相続する相続人だけでは足りません。
法定相続人全員の戸籍謄本が必要となりますのでご注意ください。
相続人の住民票
相続人の書類として、「住民票」が必要です。
住民票は新たな名義人(不動産を相続する相続人)だけで良いです。
共同名義の場合は、名義人全員の住民票が必要となります。
固定資産評価証明書
相続登記の書類として、「固定資産評価証明書」が必要です。
固定資産評価証明書は必ずご用意いただく書類です。
固定資産評価証明書とは、固定資産税を算出するために必要な書類です。
相続が発生した年度の固定資産評価証明書であることに注意が必要です。
なお、固定資産税納税通知書(課税明細書)でも相続登記には代用可能な場合もあります。
相続関係説明図
相続登記に「相続関係説明図」が必要となることがあります。
相続関係説明図とは、相続関係を略図化したものです。手書きでも構いません。
相続関係説明図が必要となる状況
相続関係説明図は、提出した書類の返却を希望する場合に必要になります。
ご希望されなければ、法務局へ提出した必要書類の原本は返却されません。
その他書類を返却してもらう方法として、戸籍謄本等は全てコピーを提出し原本還付処理することも可能です。
遺産分割協議書
相続登記に「遺産分割協議書」が必要となることがあります。
遺産分割協議後に作成するのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書が必要となる状況
相続登記の手続きの際に遺産分割協議書が必要となるのは、遺産分割協議を行った場合です。
相続人間で「誰が・何を・どれくらい」相続するのか決めた場合には、相続登記の手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割について詳しくはこちら>>
印鑑証明書
相続登記に「印鑑証明書」が必要となることがあります。
基本的には、法定相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
ちなみに印鑑証明書に有効期限はありません。
印鑑証明書が必要となる状況
相続登記の手続きの際に印鑑証明書が必要となるのは、遺産分割協議を行った場合か上申書を提出する場合です。
遺産分割協議を行うと相続登記の際には遺産分割協議書の提出が必要なのですが、その遺産分割協議書と一緒に印鑑証明書も提出する決まりとなっているからです。
上申書も同様で、一緒に印鑑証明書を提出するきまりとなっています。上申書の詳細はこの後解説します。
不在籍証明書、不在住証明書
相続登記で「不在籍証明書」「不在住証明書」が必要になることがあります。
不在籍証明書や不在住証明書は、各市町村の住民票や戸籍謄本の発行窓口にて取得可能です。
不在籍証明書、不在住証明書が必要となる状況
相続登記の手続きの際に不在籍証明書や不在住証明書が必要となるのは、住民票等の証明書類が取得できない場合です。
ただし、登記済権利証があれば、住民票等の証明書類が取得できなくても不在籍証明書や不在住証明書は不要です。
登記済権利証
相続登記で「登記済権利証」が必要となることがあります。
登記済権利証とは、登記が完了した際に登記所から買主等の登記名義人に交付する書面です。
登記済権利証が必要となる状況
相続登記の手続きで登記済権利証が必要となるのは、住民票等の証明書類が取得できない場合です。
登記済権利証があれば、不在籍証明書や不在住証明書といった他の代替書類の提出は不要となります。
上申書
相続登記で「上申書」が必要となることがあります。
上申書とは、公的機関に対して意見や報告を申し述べるための書類です。
印鑑証明書も一緒に提出が必要となりますので、別途ご用意ください。
上申書が必要となる状況
相続登記の手続きの際に上申書が必要となるのは、何か事情があって必要書類を用意できない状況である場合です。
具体的には、住民票等の証明書類が取得できない場合や、戸籍謄本により相続関係を証明できない場合に提出をします。
相続放棄申述受理証明書
相続登記に「相続放棄申述受理証明書」が必要となることがあります。
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で発行されます。
「相続放棄申述受理通知書」でも代用可能です。
相続放棄申述受理証明書が必要となる状況
相続登記の手続きの際に相続放棄申述受理証明書が必要となるのは、相続放棄をした場合です。
相続した財産が借金などのマイナス財産が多い場合、遺産の相続をすべて放棄することができます。
この相続放棄をした場合、受け継ぐはずだった不動産も放棄することになります。
相続放棄をしたら完了ではなく、不動産を相続しない旨を表明しなければなりません。
在留証明書
相続登記に「在留証明書」が必要となることがあります。
在留証明書とは領事館で発行してもらうことができます。
在留証明書が必要となる状況
相続登記の手続きの際に在留証明書が必要となるのは、相続人が海外に住んでいる場合です。
相続人が海外在住の日本人の場合、住民票が発行されません。
そのため、住民票の代わりとして在留証明書を提出しなければなりません。
署名証明書(サイン証明書)
相続登記に「署名証明書」が必要となることがあります。
署名証明書(サイン証明書)は領事館で発行してもらうことができます。
署名証明書が必要となる状況
相続登記の手続きの際に署名証明書が必要となるのは、相続人が海外に住んでいる場合です。
相続人が海外在住の日本人の場合、印鑑証明書が発行されません。
そのため、印鑑証明書の代わりとして署名証明書(サイン証明書)を提出しなければなりません。
必要書類に有効期限はある?

相続登記の必要書類の有効期限は基本的にありません!
昔収集いただいた書類でも手続き可能です。
ただし、「相続人の戸籍謄本」と「固定資産評価証明書」には注意が必要です。
相続人の戸籍謄本の作成時期
相続人の戸籍謄本については、期限はありませんが被相続人が亡くなった後に作成されたものでなければなりません。
固定資産評価証明書の年度
固定資産評価証明書については、相続が発生した年度のものということです。
【Q&A】相続登記の必要書類についてよくあるご質問

Q1,遺言書がある場合の必要書類は?
被相続人が遺言書を作成していた場合は、一部書類が不要となることがあります。
具体的には、戸籍謄本等の書類を一部省略できます。
何が省略できるかは遺言書の内容にもよります。
例えば、戸籍謄本すべてではなく、死亡の記載がある最後の戸籍謄本のみで済むなどです。
Q2,被相続人が外国人の場合の必要書類は?
被相続人が外国人の場合の必要書類は、「宣誓供述書」です。
被相続人が外国籍の場合、相続人の証明として戸籍謄本の提出ができません。海外には戸籍制度がないからです。
そのため、宣誓供述書に相続関係の旨を記載し、外国の公証人等に認証を受ける必要があります。
適用される法律に注意が必要!
日本の法律では、相続は被相続人の本国法によると定められています。
そのため、被相続人が外国籍の場合は、適用される法律から調べなければなりません。
法定相続人の定義など相続に関する法律が異なることがあります。
Q3,相続人が日本在住の外国人の場合の必要書類は?
相続人が日本在住だが外国籍の場合の必要書類は、通常通りで問題ありません。
日本に住んでいる場合は、居住地の市区町村で住民票、印鑑証明書を発行してもらえるのでそれらを提出してください。
なお、日本に住んでいない場合は、住民票や印鑑証明書を利用できません。
在留証明書や署名証明書が必要となります。
Q4,相続人が相続登記前に死亡した場合の必要書類は?
相続登記の手続き前に相続人が死亡した場合でも必要な書類の種類は変わりません。
ただし、もともとの被相続人と相続発生後に亡くなった相続人の2人分の書類を取得・提出する必要があります。
つまり、死亡した相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、死亡した相続人の相続人の戸籍謄本も必要ということです。
もとの被相続人の相続登記と、死亡した相続人の相続登記、両方の手続きを行わなければなりません。
注意!相続登記は義務となります!期限がある手続きです

相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から「3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。
3年の期限を過ぎてしまうとペナルティが課される可能があります。
また、2024年以降の相続登記について手続きをしたらいい、というわけではなさそうです。
以前の相続登記に関しても、相続登記義務化施行日より3年以内に手続きを行わなければならない可能性が高いです。
相続登記は当事務所にお任せください

「三年以内の登記義務なら三年ギリギリでもいいかな」「別に多少遅れても過料10万程度なら払えばいいかな」と油断するのではなく早め早めに対応することをおすすめします。
一方で、「相続登記と言われても何をすればいいのかわからない」「そもそも仕事や子育てでそんな時間を取る余裕はない」というような思いを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そういった方は一度相続の専門家に相談してみましょう。
一度専門家の意見を聞くことで今後行わなくてはいけないことが明確になったり、いつまでに終わらせれば良いかの目途が立ったりします。
また、場合によっては専門家に丸投げするということで自分の時間を使わずに相続登記を終わらせるという方も中にはいらっしゃいます。
当事務所では、相続登記に関するご相談を多数承っており、豊富な経験実績があります。当事務所の解決事例もご参考になさってください。
何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース>>
相続登記について疑問や不安をお持ちの方へ

当事務所では、今回のような相続登記をはじめ、相続全般に不安や疑問をお持ちの方に向けて、無料相談会を実施しております。
相続の専門家である司法書士が親切丁寧にみなさまのお話をお伺いいたします。
無料相談をご希望の方は0120-600-719までご連絡ください。
※土日祝日も応対応ですので、まずはこちらの電話番号よりお電話でその旨お伝えください。
電話相談・テレビ電話相談相談にも対応!
当事務所では、ご自宅での電話相談やテレビ相談も行っております。
コロナウイルスの影響で外出を控えられていらっしゃる方や、事務所まで遠くて行きづらいという方も、是非お気軽にご相談ください。
この記事を担当した代表司法書士

アコード相続・遺言相談室
代表司法書士
近藤 誠
- 保有資格
-
司法書士・簡裁訴訟代理認定司法書士
- 専門分野
-
遺言、家族信託、M&A、生前贈与、不動産有効活用等の生前対策
- 経歴
-
司法書士法人アコードの代表を勤める。20年を超える豊富な経験、相続の相談件数6000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
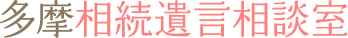


.jpg)